相続で検討することは
【お身内が亡くなられたとき】
・相続人は誰か、相続の対象となる財産は何か
→相続人調査・遺産調査
・マイナスの遺産をどうするか
→相続放棄・相続の限定承認
・遺産をどう分けるか
→遺産分割
・最低限保障される遺産の取り分があるか
→遺留分侵害額請求
【ご自身の財産を残したいとき】
・財産を誰にどのような形で残すか
→遺言
・財産の管理や承継をどうするか
→民事信託
相続人調査・遺産調査
お身内が亡くなり、相続が開始したときは、まず、(1)相続人は誰か、(2)相続の対象となる財産は何かを調査する必要があります。
(1) 相続人調査
相続人調査は、亡くなられた方(被相続人)の財産を引き継ぐ権利のある人(相続人)を確定するための調査です。
「相続人調査といっても、故人の相続人は自分たち家族しかいない」という方も多いかもしれません。
しかし、中には、両親が再婚で、元配偶者との間に子どもがいることが分かったケースがありますし、被相続人が祖父母などの場合、被相続人やその子らに離婚・再婚をした方や養子縁組・認知をした方がいるケースもあり、ご自身の認識と異なることがあり得ます。
そのため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍類を全て収集し、戸籍上の父母・兄弟姉妹・配偶者・子から相続人を特定していく必要があります。
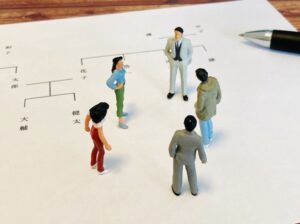
(2) 遺産調査
遺産調査は、被相続人が亡くなる時点で有していた財産(遺産)を把握するための調査です。
財産関係はデリケートな事柄であり、ご家族でも、被相続人がどのような財産を持っているかを知らないということが少なくありません。
ご自宅から財産関係の書類(通帳、証券類、権利証など)が見つかればよいのですが、被相続人と同居していなかったり、財産について話をしたことがなかったりすると、最寄りの銀行預金くらいしか見当が付かないという場合や、しばらく経ってから思いもよらない借金が判明する場合もあります。
そのため、関係各所への照会等により、遺産の内容を可能な限り調査する必要があります。

相続放棄・相続の限定承認
相続の対象となる財産は、預貯金、有価証券、不動産など(プラスの遺産)だけではありません。
借金、保証債務、税金など(マイナスの遺産)も相続の対象となります。
亡くなられた方(被相続人)が多額の借金を残していた場合、そのままにしておくと、相続人は、相続分に応じてマイナスの遺産をも引き継いでしまうことになります。
そのため、遺産調査の結果、多額の借金が見つかった場合や、他にも借金があると思われるものの総額が分からないような場合には、利害得失を検討した上で、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、(1)相続放棄や(2)相続の限定承認の手続をする必要があります。
なお、相続人が遺産の全部又は一部を処分した場合は、相続放棄や相続の限定承認が認められないことになりますので、ご注意ください。
(1) 相続放棄
相続放棄とは、プラスの遺産も、マイナスの遺産も一切相続しないことをいいます。
相続放棄の手続きは、各相続人が単独ですることができます。
相続を放棄した場合、その方は初めから相続人でなかったことになりますので、ご自身の配偶者や子が被相続人の借金を引き継ぐこともありません。
| 当事務所では、事情により相続の開始を知った日から3か月を経過した後の相続放棄や、相続の承認又は放棄の期間の伸長の手続にも対応しています。 |

(2) 相続の限定承認
限定承認とは、プラスの遺産の範囲内で、マイナスの遺産を相続することをいいます。
限定承認の手続は、相続人全員が共同してする必要があります。
限定承認をした場合、相続人は、マイナスの遺産については、プラスの遺産を限度に支払えば足りることになります。
また、ご自宅や事業用不動産など、お手元に残しておきたい遺産がある場合は、優先的に購入することもできます。

遺産分割
有効な遺言等がなく、相続人が複数いる場合、亡くなられた方(被相続人)の遺産は、相続分に従って相続人全員で共有している状態です。
そのため、個々の遺産を自由に使用・処分できるようにするには、誰がどの遺産を取得するのかを決める手続(遺産分割)が必要となります。
遺産分割の手続には、⑴遺産分割協議と⑵遺産分割調停、審判があります。
⑴ 遺産分割協議
相続放棄をせずに被相続人の遺産を引き継ぐことにした場合、相続人間で遺産をどう分けるかを話し合います(遺産分割協議)。
遺産分割協議は、通常、相続人のうちの1人又は数人から他の相続人に協議を申し入れます。
遺産分割は、相続の開始後であればいつでも行うことができ、法的な期間制限はありません。
もっとも、遺産が多額である(遺産遺産の価額が「3000万円+600万円×相続人の数」を超える)場合には、遺産分割の結果に応じて相続税を納めなければなりませんが、納税期限は被相続人が亡くなったことを知った日(通常は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内とかなり短く設定されています。遺産分割が未了でも納税期限が延長されることはなく、相続分に従って遺産を取得したものとして、各種特例が適用されない状態で一旦納める必要があります。
また、長年放置していると、今度は相続人が亡くなってしまい、相続人の相続人も含めた多人数での話し合いになる可能性もあります。
そのため、上記のようなリスクを避けるためにも、できるだけ早期に解決する必要があります。
~遺産分割協議の内容~
遺産分割協議では、原則として「相続開始時に存在し」かつ「分割時にも存在する」「未分割の」遺産を対象に、その価額を評価し、相続分に基づいて各相続人の取得額を算定します。(合意により、これと異なる分け方をすることもできます。)
被相続人の生前、相続人の一部が贈与を受けていた場合は「特別受益」として、特別な貢献をしていた場合は「寄与分」として、考慮されることがあります。
上記の取得額に応じて、各相続人が取得する遺産を取り決め、合意に至れば遺産分割協議書を作成することになります。
| 当事務所では、相続人間で合意できる場合の遺産分割協議書作成の他、感情的対立や法的対立(遺産の範囲、遺産の評価、特別受益、寄与分、分割方法など)により話し合いが困難な場合の交渉代理を行っています。 |

⑵ 遺産分割調停
遺産分割協議での解決が見込めない場合は、相続人のうちの1人又は数人から、他の相続人全員を相手方として、遺産分割を請求する調停を申し立てることになります(遺産分割調停)。
申立先は、相手方(複数いる場合は任意の1人)の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所です。
遺産分割調停は、調停委員会(原則2名の調停委員と1名の裁判官で構成されています)の主催のもと、被相続人の遺産をどう分けるかを話し合う場です。
遺産分割調停での話し合いは、当事者の一方が調停室に入って調停委員と話をし、その後交代で他方の当事者が入って調停委員と話をし、調停委員から相手の言い分も聞くという形をとります(1調停期日あたり各当事者2回、1回20~30分程度であることが多いです)。
~遺産分割調停の進め方~
遺産分割調停は、以下のような流れで進行します(段階的進行モデル)。
ア. 相続人の範囲
相続人が誰であるかを確定します。
戸籍が事実と異なるとの主張がされるなど、相続人の範囲に争いがある場合には、人事訴訟等の手続が必要です。
なお、相続人の中に認知症などで判断能力に問題のある方がいる場合には、成年後見等の手続が必要になります。
![]()
イ. 遺産の範囲
遺産分割の対象とする遺産の範囲を確定します。
遺産分割の対象は、原則として「相続開始時に存在し」かつ「分割時にも存在する」「未分割の」遺産です。遺言書や遺産分割協議書で既に分け方が決まっている財産は、遺産分割の対象になりません。
被相続人の遺産に含まれるかに争いがある場合には、民事訴訟の手続が必要になります。
なお、遺産分割前に相続人の一部により処分された財産について、処分者が認定できる場合には、(他の)相続人の同意により遺産分割の対象とすることがあります。
![]()
ウ. 遺産の評価
上記イで遺産分割の対象とした遺産の評価額を確定します。
特に評価が分かれやすいものとして、不動産や非上場株式などがあります。
合意できない場合には、鑑定が必要になることがあります。
![]()
エ. 各相続人の取得額
上記ウで遺産の評価額が確定すると、相続分に基づいて各相続人の取得額が決まります。
ただし、「特別受益」や「寄与分」が認められる場合には、それらを考慮して各相続人の取得額を修正します。
![]()
オ. 遺産の分割方法
上記エの取得額に応じて、各相続人に遺産を分割します。
遺産の分割方法には、物自体を分ける(現物分割)、物を分けて差額を金銭で調整する(代償分割)、売却して金銭を分配する(換価分割)などがあります。
![]()
上記ア~オについて合意に至れば調停成立、合意に至らなければ調停不成立となり、裁判官が判断する手続(審判)に移行します。
このように、遺産分割調停では、順を追って問題を整理・解決しながら最終的な合意を目指すものとされており、当事者は、各段階に応じた適時適切な主張・根拠を提出し、調停委員と相手方を説得する必要があります。
| 当事務所の弁護士は、遺産分割調停の実務上の取扱いや関連する審判例・裁判例にも精通しており、事実関係と証拠を法的観点から整理し、調停に代理人として出頭・同席することで、ご依頼者のお考えを説得的に伝えるお手伝いをします。 |

遺留分侵害額請求
遺留分とは、相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保障される遺産の取り分です。
他の相続人や第三者が亡くなられた方(被相続人)の生前に贈与を受けたり、遺言によって遺贈を受けたりすることにより、相続人の取得額が遺留分額を下回る場合には、遺留分が侵害されているとして、その差額を請求することができます。
〜遺留分侵害額の算定方法〜
| 遺留分率は1/2(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)であり、相続人が複数いる場合、これに各相続人の相続分を乗じたものが、各自の遺留分割合となります。・・・[a] |
| 遺留分算定の基礎となる財産額は、「相続開始時におけるプラスの遺産の額」+「相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内)」+「第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内)」-「マイナスの遺産の額」です。・・・[b] |
| 上記[a]×[b]が遺留分額です。・・・[c] |
| 遺留分侵害額は、上記[c]の「遺留分額」-「遺留分権利者が受けた特別受益の額」-「遺留分権利者の具体的相続分に相当する額(遺産分割の対象財産がある場合)」+「遺留分権利者が負担するマイナスの遺産の額」で算定されます。・・・[d] |
なお、上記[d]の遺留分請求権者が受けた特別受益については、上記[b]の相続人に対する生前贈与と異なり、10年以内のものであるか否かを問いません。
遺留分侵害額の請求には期間制限があり、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内(かつ相続開始から10年以内)に行使する必要があります。
| 遺留分侵害額の算定や行使には難しい点が少なからずあります。「遺留分が侵害されているかもしれない」と不安に思われましたら、ご相談ください。 |

遺言
遺言は、ご自身が亡くなった後、財産を誰にどのような形で残すかなどを決めるための意思表示です。
遺言により、ご自宅や事業用不動産を後継者の方が相続することにしたり、相続人以外の方に財産を残したりと、法で定められた相続とは異なる形にすることができます。
遺言の種類には、主に(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言があります。
(1) 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者ご本人が遺言書の全文、日付及び氏名を手書きし、これに押印することが必要です。
加除・修正する場合は、ご本人がその場所を指定し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつその変更の場所に押印しなければ効力を生じません。
自筆証書遺言の方式緩和により、全文自書の例外として、相続財産の全部又は一部の目録(財産目録)を添付する場合には、財産目録については自書することを要しないとされましたが、この場合、財産目録の毎ページに署名押印することが必要とされています。
自筆証書遺言が上記の方式に違反している場合には、残念ながら無効となってしまうリスクがあります。
また、内容が不明確だったり、執行を見据えた内容になっていなかったりすると、ご本人の意思が実現できなかったり、改めて手続(遺言執行者選任申立や遺産分割協議など)が必要になってしまうことがあります。
なお、遺言書保管制度により、自筆証書遺言に係る遺言書(上記の方式及び所定の様式で作成したもの)を法務局に預けることができるようになりましたが、遺言の内容については関与しないとのことであり、弁護士等の法律の専門家に相談することが推奨されています。
~遺言内容の検討の視点~
ご本人の意思が確実に実現できるよう、なるべく解釈の余地がない一義的に明確な内容である必要があります。
後日における相続人間の紛争(遺産分割協議、遺留分侵害額請求など)を生じさせないよう、対象財産の特定や遺留分に配慮することも重要です。
遺言の内容を速やかに実現するためには、遺言執行者を指定し、必要に応じて権限を付与することも検討します。
| 当事務所では、遺言に関する紛争や遺言執行に対応してきた経験があり、その知見も活かしながら、ご本人の希望や事情を可能な限り反映した実効性のある遺言書を作成できるようサポートします。 |

(2) 公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者ご本人が、遺言の内容を口頭で告げ(口授)、公証人が、これを文章にまとめたもの(筆記)をご本人と証人2名に読み聞かせ又は閲覧させ、内容に間違いがないことを承認、署名押印してもらった上で、公正証書として作成します。
実務では、ご本人又はその依頼を受けた弁護士等が、公正証書遺言を作成したい旨を公証人に連絡し、公証人が、遺言の内容を聞き取って筆記しておき(当事務所では、ご本人と協議・検討した内容を条文化し、メールやFAXで公証人とやりとりします)、作成日においては、公証人が、ご本人の口授する遺言の内容が筆記の内容と同一であることを確認し、ご本人と証人2名に読み聞かせる等の手続を行います。
公正証書遺言は、国の公務である公証作用を担う公証人の面前で作成されるものであり、方式違反で無効とされる可能性が低く、自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用する場合を含みます)に比べて安心といえます。
| 公正証書遺言の作成手続をご依頼いただくと、弁護士が遺言の内容・手続面でのサポートをすることに加え、公証人が関与することで、より確実性の高い遺言となります。 |

民事信託
民事信託は、ご自身の財産をどのように管理・運用・処分したり(財産管理)、ご自身が亡くなった後、財産を誰にどのような形で残すか(財産承継)を決めるための制度です。
典型的には、ご自身を「委託者」 、信頼できる方を「受託者」、ご自身又はご家族を「受益者」として、委託者と受託者の間で信託契約を締結し、契約で定めた目的・方法に従って財産管理を受託者に任せ、そこから得られる利益を受益者が受け取る(次の受益者を指定することで財産承継も可能)というものです。
民事信託により、
・ご自身の判断能力が低下しても、財産管理を継続することができる(認知症対策)
・高齢や障がいのあるご家族のために財産を残し、その管理を委ねることができる(福祉型信託)
・自社株や事業用不動産の承継先を二世代、三世代先まで指定できる(事業承継対策)
など、柔軟かつ幅広い活用が実現できます。
~民事信託と弁護士の役割~
(1) 信託契約書等の作成
信託契約書や、民事信託に関する遺言書(遺言による信託の場合)、自己信託設定証書(自己信託の場合)の案を作成します。
委託者ご本人の希望や想い、事情を詳しく伺った上で、信託スキームを設計し、信託法の規定を踏まえながら、オーダーメイドで信託条項を起案します。
(2) 関係機関との調整
・信託口口座を開設する必要がある場合には、金融機関と打ち合わせをし、受託者名義の信託専用口座の開設手続をサポートします。
・信託契約書を公正証書にする場合には、契約書案の内容や作成手続について、公証人と連絡調整します。
・信託財産に不動産が含まれている場合には、登記申請手続(信託を原因とする所有権移転及び信託の登記)を依頼する司法書士との橋渡しをします。
・信託の各段階(設定時、信託期間中、終了時)の課税関係について、税理士と打ち合わせをし、税務リスクに備えます。
| 当事務所では、民事信託に関する上記各業務を行っています。財産管理や財産承継を検討されている方はご相談ください。 |

